あれもこれもどれもそれもなにもかにも欲しがってちゃ身がもたないね ― 2003年10月19日 22時14分
◆ 『武満徹: フォー・アウェイ、遮られない休息、他』Pf高橋悠治 (Grammophon, 1973/1994)を聴き、悠治のライナーを読み返すたびに、音がしじまに消え行く瞬間が武満の音楽からなくなったのはいつなんだろう、と思う。『鳥は 星形の庭に降り立つ』(1977)あたりがその境界にあるんだろうか。燦然と輝くペンタトニック和音、それがその後の武満であり、それがしじまへと消え行 くエンディングがそれまでの彼のありよう、おんぼろピアノの減衰音の移ろいに耳を寄せる孤独な男、であるようにも思える。それでいて案外どちらの武満も捨 てがたいと自分なんかは思っていることに気が付く。
◆ 山崎まさよしは弾き語りライブ盤"One Knight Stands"(Polydor, 2000)を以前知り合いから借りて、うーんギターめちゃ上手い男だけどCDで聴く音楽じゃないよなあと思って暫く様子見にしていたが、最近改めてスタジ オ盤を図書館で借り出してみる。"Transition"(Polydor, 2001)はそんな先入観を取っ払ってくれる、ポップソングとしての作りを大事にした作品。同時期のスガシカオがどことなくマンネリ化してたのとは好対照 に新境地を見せる。この盤に較べて1998年リリースの『ドミノ』は、やはりギターマンとしてのテイストが強すぎて私にはちょっと取っ付きにくかったで す。
◆ "Sweet"(Kitty, 1999)でちょっと飽きが来てこれまた遠巻きにしていたスガシカオもこの機に復習。"4 Flusher"(Kitty, 2000)ってタイトルもどうかと思ったしシングル曲は魅力なかったしで今頃聴いてるのだけど、アルバム全体もそんな感じで。一番好きなのが彼お得意のと ぼけた笑いを誘う「ドキュメント2000 -The Sweetest Day Of My Life-」だったりして。それってスガの魅力の中心ではないはずなんだけど本来。 もう1枚、アコースティック(? そういう風には聴かなかったけど)アルバムとして出ている"Sugarless"(Kitty, 2001)も、一部過去のシングルカップリング曲などを含む寄せ集め的編集のせいもあってか、楽曲のインパクトが弱い。「マーメイド」は名曲だと思うし、 「ひとりぼっち」は拾い物だったけど、全体の印象は薄い。
◆ 音楽話はさらに何故かChick Coreaのピアノソロ、Caetano Velosoの歌うラテンスタンダードと続くのですがまた改めて。
Maria, Maria ― 2003年09月30日 22時56分
◆ 正直、最初のうちはどうなることかと気が気でなかった。1曲目、Miltonなしでのインスト。だが何というか、ピンでステージを張るにはもう一歩という バンドに思えて不安になる。もっとも、これってIvan Linsのバックがドラムス=Teo Lima/カヴァキーニョ&ヴィオラォン=Ze Carlos/キーボード=Marco Britoという最強トライアングルだったのに較べてなので、言っては酷という気もするのだが。 さて2曲目でMilton登場...と思ったらツインヴォーカルのようなのである。Marina Machadoという女性シンガー。Leila Pinheiroを思わせる艶やかで張りのある声。悪くない、というか、かなり良いです。でも、彼女がメインでMiltonがサブ? うーん。しかもMarina元気に踊る踊る、Milton棒立ちのまんま気のない感じで指揮してる。うーん。大枚はたいて聴きにきたのってコレだったの、 みたいな気分で最初の数曲は過ぎる。
◆ だが段々とMiltonの歌の比重も増えていって、最初ややかすれ気味で心配していた声も段々と芯が強く伸びやかになっていき、ファルセットも期待を裏切 らない美しさを聴かせはじめ、ようやく安心してショウの流れに身を任せられるようになってきた。あとはもう怒濤の名曲オンパレード、アコーディオンで聴か せる'Ponta de Areia'なんてのもなかなかグッと来て、最後は'Caxanga (Os Escravos de Jo)'、そしてアンコール、来ました'Maria Maria'! 会場に歌えと煽るMilton(でも動きは相変わらず素っ気ない)。Miltonと一緒に歌ってるなんて何て幸せなんだ、というわけで終演の頃にはすっか り心の収支は黒に転じているのだった。そう、基本的になべぞうさんの書かれているとおりなんであります。Miltonの歌声はやはり特別だった。それと唱和できたなんてもう、後のことはどうでもいいのであります。
◆ ただ、Miltonはやっぱり違う、ということを噛みしめながら同時に、意外なことを感じた。あの、まあ、気のない立ち姿勢のせいも若干はあるのですが、 Miltonの歌声ってなんか「オトーサン」なのである。よく「ブラジルの声」とか「神秘的な」とか言われてて(で、そういうのってあまりにオリエンタリ ズムじゃないのーと思えてあまり馴染めない見方なんだけど)、何となくそういう意味で特別なのだと自分も頭では考えていたようなのだけれど、生で聴いた ら、実はそうではなかった。すっごく、ものすごく「人間くさかった」。そのとてつもなく芯の太い人間くささこそが、Miltonの歌声を特別ならしめてい る---少なくとも自分にとってはそうだった。オトーサンが何のてらいも飾り気もなく、本音を地声でお腹の底からすとーんと吐き出してしまう、そういう 「強さ」、そこにいたく感動してまったのだ。ありがとう、オトーサン。
◆ 何だか違う、と思ってるMilton好きの方がきっとたくさんおられると思うので恐縮ではありますが、自分としてはこれ以上ない賛辞のつもりであります。はい。
この星は青くて丸い屑籠 ― 2003年08月07日 11時13分
◆ さて夏休みなのですが。日々これといって何をやるでもなく。息子のピアノのコーチをしている手前上またソナチネやらソナタやらをおさらいしてるので、少し上達しました。でも昔こんなもの弾いてたのかと思うと結構驚愕です。特にモーツァルトのソナタなんか。聴いててあんなに耳心地よいのに、まあ指がちゃんと回らないとどうにもならないっていう基礎テクニック徹底重視型の速弾きスケール/アルペジオ。うわ。
◆ で弾いてて思うのは、音楽山ほど聴いてきた今のほうが、圧倒的に曲を解釈する→表現する能力は深まっているのに、技術のほうはめっぽう後退してるのだなあ、と。天は凡人には二物を与えないようである。はあ。
◆ で空いた時間でCD整理など。そのうちまたじっくり聴こうと思ってた盤をきちっと掘り出すことになる。その中からまずは、Leila Pinheiro: "Catavento e Girassol" (EMI,1996)を掛けてみた。うーん、以前のコメントってアテにならない。これは気持ちいいわ。当時はタイトル曲の良さに惹かれすぎていて他の楽しみ方がわからなかったのかも知れず。Guingaの書くひねったサンバ、これはこの夏オススメです。なんか中身のないコメントだなあ。
◆ はい、久々に身軽報告です。めっぽう身軽です。この1年ほど、ときどき-1とか+2くらいするものの、すぐに標準体重に戻るという安定ぶり。やはり基礎代謝レベルを上げておくことは重要です。ジム+水泳という組み合わせのメニューを時々こなして来ますが、これってハノンとソナチネ、みたいなバランスで気持ちいいです。
ありのままのスタイルで行こうじゃないか ― 2003年08月04日 10時24分
◆ キリンジ『スウィートソウル ep』(東芝EMI, 2003)、ようやく思い立って買って、その渋させつなさに日々ヘヴィロし、日々泣いてます。て言うんじゃ説明になってないですけど。詳しくはまたにして、とりあえず一つ。アートワークと楽曲構成。これが異様。EPっつうのに6曲入りで、まるまる6曲分のカラオケがそのあとぶっ続けで入ってるっていうこの構成はどうか。聴いてみるとこの抜け殻感はちょっと尋常ではない。振り返ってジャケット見てみると、暗闇に浮かぶコンビニ風の建物。裏ジャケはその遠景。をを、キリンジの原風景たるサバービア。サバービアとはつまり大量生産・大量消費の生活インフラであったことよ、と改めて思い出す。そうすると例のカラオケ6曲がウォーホルのスープ缶のように思えてくる。抜け殻としての工業製品。キリンジが根底においてサバービアのサウダーヂを刻み続けていることとの、何という見事な一致。
◆ さーてサウダーヂといえばブラジルです(若干強引な振り)。前からやろうやろうと思ってはいたのですが、ようやく「ポ語邦訳DIY」、第2回を掲載しました。うーん、Fernando Brantなんてやるもんじゃないな。難しすぎ。きっと間違ってると思う。誰か直して下さい。切にお願い。
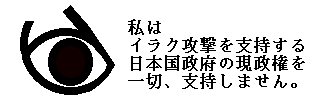
最近のコメント